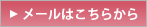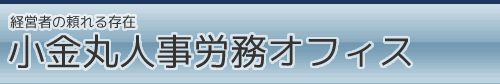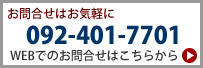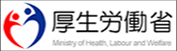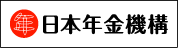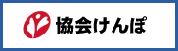のみを指すのではなく、「世間の人たちが持つ価値基準に、企業活動や社員の判断や言動がずれていないか?」ということも含みます。
のみを指すのではなく、「世間の人たちが持つ価値基準に、企業活動や社員の判断や言動がずれていないか?」ということも含みます。【動機】 無理難題な指示(目標、納期)に対し、その指示の重みやできなかった場合の叱責などを考え、法令やルールを理解していても、また悪いことと重々承知していてもそれを破ってしまう可能性がある。
【機会】 動機があっても、チェックされ見つかってしまったり、責められ、処罰されたりする可能性が高ければ実行しないが、その可能性が低くければ、やってみようと思ってしまう。
【正当性】 たとえ発覚しなくても、それが許されないことだと考えれば思いとどまれるだろうか?「法令に違反しているわけではない。」「業界の慣例じゃないか。」「目標達成のためには手段は選べない。」「他の人も同じようなことをやっているじゃないか。」
この三つが揃って、不正が行われるという考え方です。
対応策としては、「動機」と「正当性」に焦点をあてるということです。
【動機】 与えた目標により、現場に不正や不祥事やトラブルを引き起こすような動機が生まれることがないだろうか?仕事の与え方、指示に無理があり、動機の生まれやすい現場はないだろうか?という観点で検証しなければならない。
【正当性】 良からぬことを思いついた、それを実行するチャンスもある、後はやるかやらないか。悪いと分かっていることをやるときには、「仕方がない」「大したことだはない」「皆がやっていることだ」といった正当化、気持ちの整理が必要になる。
不正な動機をゼロにすることは難しい。またパーフェクトな「管理体制を敷くことも無理である。不正を防ぐには、「正当化」をさせないことが重要だ。それには、「自社らしい対応とはなにか」を共有することが必要だ。顧客や社会と対峙する姿勢を定めた言葉、企業理念や行動規範を社員に理解させ、浸透させることが効果的である。経営者、現場の上司が、自らそれを実行しているところを見せ、社員に折に触れ語りかけなければならない。
企業理念や行動規範は、不正や不祥事を防ぐための、最後の砦である。企業理念や行動規範を浸透させ、一人ひとりが何かの折には胸に手を当てて誠実な行動選択ができるような理念・規範の浸透状況を作ることが重要である。
「法令には違反していない。」とか「それはそんなに大きな問題ですか。」といったトップの発言を聞くと、「コンプライアンス=法令遵守」という勘違いがあるのではと思います。顧客や社会は、法やルールを守っていればOKとは言っていません。
(トラスコ中山 HPより)
物事の判断をするときには、「損なのか、得なのか」の損得勘定ではなく、「正しいのか、間違っているのか」と自問自答の上、必ず損得勘定抜きの「正しいこと」を選ぶ。
ご参考にしてください。
〜就業規則・労務相談は、
小金丸人事労務オフィスへ〜
816-0811 春日市春日公園1-12-205
TEL092-401-7701 FAX092-405-5167